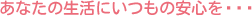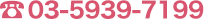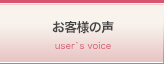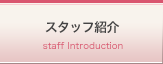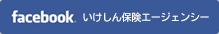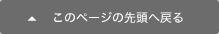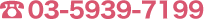最近では働き方改革が盛んに行われています。
もちろん大切な社員には心身ともに健康であって欲しいですし、社員の健康を確保することは彼らの最大のパフォーマンスを引き出し、会社の利益にもつながります。
しかしそうはいっても、人手不足も相まってなかなかすぐに業務量を減らすことは難しいと思われます。
そして、実際に労働災害が起きてしまった場合、会社には社員に対する損害賠償責任が発生します。
本日お伝えするのは、この社員への損害賠償額が近年増加し、会社にとってのリスクも増大しつつあるという事実です。
今回は実際の事例をご紹介しつつ、このリスクに対応するための対策についてもご説明します。
従業員に対する損害賠償件数は増加傾向にある。
まず、賠償額が増えているだけでなく、従業員から会社への賠償請求件数そのものも増加しています。
その理由として、
1.2008年3月からの労働契約法により企業側の安全配慮義務・健康配慮義務が明確化されたため。
2.スマホ・ネットの普及により、企業を訴えると賠償金が得られるということが認知されるようになった。
3.挙証責任(きょしょうせきにん)が従業員から会社へと移った。
4.2018年6月からの残業規制法案(働き方改革)により、一層企業側の責任が明確化に。
の4つが考えられます。
1.2008年3月からの労働契約法により企業側の安全配慮義務(健康配慮義務)が明確化されたため。
労働契約法では、企業側に、社員に対する安全配慮義務(健康配慮義務)があることを明示しました。
安全配慮義務とは、会社が、労務を提供する社員に対して安全な労働環境を整備する義務を指します。ですから、社員が労災事故でケガを負った点につき、企業が安全な労働環境を整備していなかったと認められた場合、責任を負うことになります。
安全配慮義務は健康配慮義務という言葉で表されることもあるように、肉体労働における安全配慮のみならず、社員の心身の健康への配慮も含みます。
例えば、社員がうつ病で休業し、復帰後再度うつ病になった場合、社員の心身の健康を確保するために必要な配慮を怠ったとして、企業側の責任が問われます。
またうつ病だけでなく、慢性の持病(高血圧、糖尿病など)を患っている従業員への配慮も必要と考えられています。
2.スマホ・ネットの普及により、企業を訴えると賠償金が得られるということが認知されるようになった。
以前は、そもそも従業員が企業を訴えるようにも何が必要か分からないなどの理由で、企業を訴えることが一般的ではなかったと思われます。しかし、スマートフォン・インターネットの発達により、訴訟のやり方、他に従業員が会社を訴えて成功したケースなどを簡単に知ることができるようになりました。これにより、以前より従業員が会社を訴えることのハードルが下がりつつあるのです。
3.挙証責任(きょしょうせきにん)が従業員から会社へと移った。
挙証責任とは、裁判において、訴訟の内容が正しい、もしくは誤りであると証明する責任のことです。挙証責任が会社へ移ったということは、例えば会社が安全配慮義務に違反していると従業員に訴えられた場合、従業員がその内容は正しいと証明するのではなく、会社がその内容が誤りであると証明しなければならないことを意味します。
これにより、従業員からすると裁判における労力が減り、訴訟へのハードルが下がると言えます。
4.2018年6月からの残業規制法案(働き方改革)により、一層企業側の責任が明確化する。
これは、安全配慮義務が労働契約法で明示化されたのと同様です。過労の問題などにおいて企業側の責任が明確になり、従業員にとって有利になります。
5.損害賠償の額も増加傾向にある。
賠償の件数だけでなく、その額も増加しています。
その理由としては、障害年金の給付金を賠償金から控除できなくなったという点があります。
というのは、これまでは将来もらうであろう障害年金を賠償金から差し引いて賠償金額を計算していたところ、障害年金は賠償金支払い時点では受給していないという理由で、近年ではこの額が差し引かれなくなってきているためです。
例えば、賠償金が2億円の場合
従来:賠償金2億円ー将来の年金給付1億2,000万円 = 支払賠償金8,000万円
近年:賠償金2億円 = 支払賠償金2億円
と変化しています。
実際にこれにより、支払額が大幅に増額されています。
賠償事例の紹介
事例1
認容額:3,237万円
事案概要:自宅で倒れ病院に搬送されたが、脳出血で死亡。過重な業務に従事したことが原因とされ、企業側の安全配慮義務違反による損害賠償責任が認められる。
事例2
認容額:5,044万円
事案概要:高速道路を走行中、前方の大型貨物自動車に追突し死亡。企業側の「役員(個人)」が超過勤務をさせた為であるとして、連帯しての損害賠償が認められる。
事例3
認容額:1億3,532万円
事案概要:従業員が自宅で突然死。著しく過重な業務ではないものの、1か月300時間を超える拘束時間の長さ等からみて、肉体的・精神的負担が大きく突然死を招来した。また、指揮命令下のもと労働 契約関係と同様の指揮命令関係があったことは明らかで、心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を払うべきとし、損害賠償が認められる
事例4
認容額:1億8760万円
事案概要:就寝中に心室細動を発症し低酸素脳症により意識不明で寝たきりの状態となる。203日間の連続出勤をしており長時間労働によるものとして損害賠償が認められる。
事例5
認容額:1億9870万円
事案概要:人事異動直後、勤務中に小脳出血・水頭症を発症し手術を受けたが、継続して半昏睡状態となり体を自由に動かすことができなくなった。異動後間もない段階で慣れない業務を担当しており、発症までの12日間における時間外労働時間は61時間、1か月に換算すると約152時間30分に相当する状況。質的・量的に著しく過重であったというべきであり、本件発症との間で相当因果関係を認めざるを得ないとし損害賠償責任が認められる。
このように、損害賠償の額が大幅に上がり、企業のリスクは増加しています。
中小企業で一度にこの額の賠償責任が発生すれば、経営問題に発展しかねません。
損害賠償リスクへの対策
このような増大するリスクへの対策として、弊社では雇用慣行賠償責任補償・使用者賠償責任補償という保険への加入を推奨しています。
使用者賠償責任補償とは、近年増加している「うつ病自殺」「過労死(脳・心疾患)」「ケガによる労災事故」等により、従業員及びご遺族から賠償金を求められ、企業または役員が負担する法律上の損害賠償金への補償です。
雇用慣行賠償責任補償とは、「雇用上の差別」「セクハラ・パワハラ」「不当解雇」等により、発生し、企業または役員、従業員が負担する損害賠償金への補償です。
これらの補償は本来、ご遺族の方の生活を守るという目的があります。
しかしそれだけでなく、会社を守ることで、残った社員の生活を守ることにもつながるのです。
実際に中小企業ですと、鬱や過労死への多額の賠償金で、会社が倒産することもざらにあります。
賠償リスクは増大しつつあります。ぜひ保険に加入することで備えてください。
保険は分かりにくいことも多いと思いますが、弊社では分かりやすい保険の説明を心がけております。
ぜひお気軽にご相談ください。